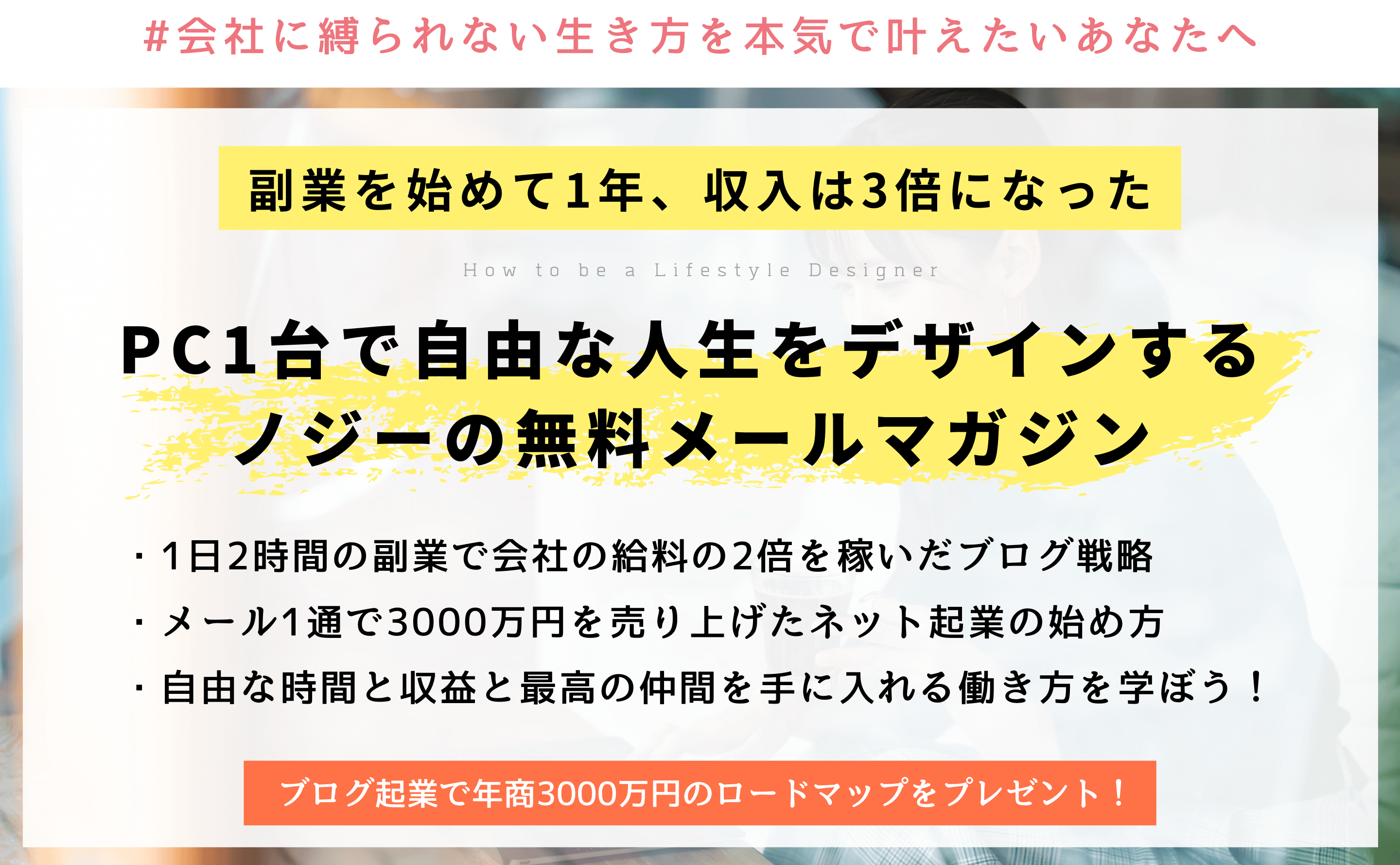この記事では、ブログで収益化したい初心者の方に向けて、読まれる記事をゼロから書き上げるまでの手順を解説します。
- ブログをやっているけど記事の書き方に自信がない。
- 頑張って記事を書いているけど、結果に繋がるか不安。
- これからブログを始めるから基本的な記事の書き方を学びたい!
こんなお悩みを解決する上で、最優先で取り組んでいくべきは「記事を書く手順」をマスターすることです。
一方でブログでなかなか成果が上がらない人は、なんとなく思いついたことをただ書いていくばかりで、記事を戦略的に作る意識が欠けがちです。
ぜひ、この記事を参考にしながら、読まれるブログ記事の書き方と手順を理解していただき、サクサクと記事を書けるようになり、アクセスアップを実現していきましょう。
ブログを書く上で最も大事な2つのこと
新しくブログ記事を新規投稿する際、いきなり本文から書き始めていませんか?
もし自由にブログ記事を書くことが目的なら、それでも全く問題ありませんが、ブログでアクセスを増やしていったり、収益を上げていきたいのであれば、いきなり記事を書き始めるのはNGです。
戦場に出る前に、まずは戦略を立てることから始めましょう。
ブログにおいては、
- 何を目的にした記事なのか。
- 誰にどんな価値を届ける記事なのか。
特にこの2つは事前にしっかりと固めておいてから、実際の記事作成に移っていきましょう。
何を目的にした記事なのか
ブログ記事といっても、記事によって目的は様々です。
- アフィリエイト報酬を得る
- アドセンスで成果を出す
- 見込み客リストを獲得する
- 読者にファンになってもらう
- SNSでのバズを狙う
- 被リンクの獲得を狙う
などなど、1つのブログの中でも記事によって目的が異なることも一般的です。
もし、そのブログ記事の目的がアフィリエイト報酬を獲得することであれば、「いかに商品を成約してもらうか」から逆算して記事を設計していく必要がありますし、アドセンスで収益を得ることが目的であれば、いわゆるコピーライティング的な要素は記事の中で不要になります。
検索エンジン経由でアクセスを集めることが目的であれば、SEOを意識した記事を作る必要がありますが、SNSでバズを狙ったり、あるいはブログ読者にファンになってもらうことに特化するのであれば、過度にSEOを狙うことは逆効果になることも考えられます。
記事の目的によって、記事を書く上で大事になるポイントも当然変わってくるものです。
だからこそ、まずは「今から書く記事の目的は何なのか」を明確にした上で、記事作成を進めていく必要があるのです。
誰にどんな価値を届ける記事なのか
ブログ記事を書く上での「目的」が定まったら、その目的を達成するために、誰にどんな価値を届ければいいのかを明確にしましょう。
なぜなら、ブログは自分本位で書いて結果が出るものではなく、読み手に対して価値のあるコンテンツを作ることで、アクセス数や売上、コンバージョン数といった結果に繋がっていくからです。

好き勝手にブログを書いて結果が出る人は、自分の好き勝手と世間の需要が奇跡的に一致する人か、自分の好き勝手に需要がある有名人か、どちらかですね。
価値の受け取り方は、受け手次第ということになるので、まずは「誰にどんな価値を届ければ、目的達成ができるのか」を整理していきましょう。
特定の商品をアフィリエイトしたい場合は、その商品を成約してもらうことが記事を書く目的になります。
そのためには、成約に近いキーワードで検索上位をとって、記事経由で成約をしてもらえば良いことになるので、「その商品を必要としている人は誰で、どんな悩みを持っているのか(=ターゲット)」を考え、「その商品を成約してもらうには、どんな導線を作ってあげればいいか(=価値)」を考えることが必要ですね。
ブログ記事を書く手順①:記事を書く前にやること
ブログ記事を書く時は、実際に記事本文を書き始める前の下準備が最も大事と言っても過言ではありません。
まずは、以下に挙げる4つを確実に、記事を書く前に行うようにしましょう。
- キーワード選定
- キーワードの検索意図を把握
- 読者にとってほしい行動を決定
- 記事構成の決定
キーワード選定
記事の目的、そしてターゲットと提供する価値が見えてきたら、次は具体的なキーワード選定を行っていきます。
検索者は自分が解決したい悩みや疑問を解消する手段として、キーワードを打ち込んで「検索」を行い、検索結果画面に表示されたブログ記事の中から、自分の悩みが最も解消されそうなタイトルをクリックし、記事を閲覧します。
つまり、ブログ記事を書く時は「どのキーワードで上位表示を狙うか」を決めることになりますが、自分がターゲットにしている読者は何というキーワードで検索をするかを考えることが重要です。
キーワード選定をする際には、
- GoogleやYahooのサジェストを参考にする
- キーワードプランナーで月間検索ボリュームを見る
- SNSやQ&Aサイトからリサーチする
- 検索者の気持ちになって、何て検索するかを想像する
といったアプローチが効果的ですが、ツール等を使うにしても「検索者心理」を最優先して考えることが何より重要です。
キーワードの検索意図を把握
上位表示を狙うキーワードを決めたら、キーワードの検索意図を把握しましょう。
ブログ記事では、検索経由でブログに辿り着いた読者に対して価値提供をする必要がありますが、そのキーワードで検索した理由や知りたいこと、満たしたい感情を知ることができなければ、記事の書きようがありません。
検索意図を把握するためには、
- 実際に上位表示されている記事を参考にする
- Q&AサイトやSNSを参考にする
- 実際に同じ悩みを持ってそうな人に聞いてみる
- 検索者の気持ちになって徹底的に考える
などがありますが、検索者が置かれた状況を徹底的にイメージすることが重要です。
読者にとってほしい行動の決定
つまり「記事の出口」を決定するということです。
アフィリエイトで成約を狙う記事なのか、ブログに集客をすることが目的の記事なのか、SNSでバズらせることを狙う記事なのか、成約を狙うキラーページにアクセスを流すための記事なのか、記事の目的によって記事の構成や書き方は変わってきます。
そして、記事の目的とは「最終的に読者にとってほしい行動」によって決まります。
例えば、アドセンス主体のトレンドブログや、ファンづくりのための記事であれば、明確な出口を用意することは難しいかもしれませんが、トレンドの場合は「知りたいことが知れた(願わくば広告もクリックしてほしい)」くらいで、ブランディング目的であれば「サイト(or 運営者)に対するイメージが変わった」くらいでもOKでしょう。
大事なことは、自分なりに「この記事を読んでもらった結果、とってほしい行動や態度変容は何か」をイメージすることです。
ブログ記事を書く手順②:記事を書く時にやること
しっかりと事前準備ができたら、次はいよいよ記事作成ですが、いきなり記事本文を書き始めるような真似はNGです。
記事を書く際にも上から下まで一気に書いていくのではなく、
- 記事のタイトルを作る
- 記事の構成(見出し)を作る
- 記事の本文を書く
という3ステップで確実に質の高い記事への道を歩んでいきましょう。
記事のタイトルを作る
まずは記事の本文を書き始める前に、記事タイトルを作りましょう。
タイトルを作る際には、以下の要素を意識すると良いです。
- 選んだキーワードを適切に入れる
- 狙ったキーワードの検索意図に合ったタイトルにする
- できる限り検索されるキーワードを多く使う
- 極力タイトルは32文字以内でつける
- 検索者がクリックしたくなるように意識する
特に初心者の頃は「キーワードの詰め込みすぎ」に気をつけましょう。
たくさんキーワードを詰め込みすぎて、検索者にとって気持ち悪い日本語にならないようになったり、検索者の知りたい情報が含まれていそうなタイトルにならなくなってしまったり、というケースは非常に多いです。
また、他の上位表示されている記事と同じようなタイトルになってしまうのもよくないので、他の記事と並んだ時にこの記事をクリックしたくなるかどうかという尺度も持ち合わせるようにしてください。
記事の構成(見出し)を作る
ブログ初心者の頃は「上から順に本文を書いていって、その都度、見出しをつけていく」という書き方をしがちですが、それだと記事の構成がぐちゃぐちゃになってしまいます。

読者にとっても読みづらく、情報が整理されていない駄記事になります。
従って、記事タイトルを決めた後は、読者にどんな順番で何を伝えればいいかを整理した上で、最初に見出しを作ってしまいましょう。
まずは記事の骨組みを作った上で肉付けをしていくイメージです。
ブログ記事の見出しの作り方について詳しく知りたい場合は下記リンク先をご参照ください。
参考:ブログSEOを意識した見出しの付け方のルールと見出しの書き方
記事の本文を書く
記事タイトルが決まり、全ての見出しを作り終えてしまったら、いよいよ記事本文のライティングです。
とはいえ、タイトルと見出しができている時点で記事は8割型完成と言っても過言ではありません。

見出しができている時点で「何を書けばいいか」は整理できていますから、それについて詳しく書いていくだけですね!
たまに「記事本文を書いているうちに何を書けばいいかわからなくなってしまう」という相談を受けますが、その時点で「構成がちゃんとできていない」ことになってしまいます。
タイトルと見出しが決まれば「何を書くべきか」は自ずと明確になるわけですので、あとはその見出し内で書くべきことを、読者にとってわかりやすい文章で書いていきましょう。
記事本文を書くときも「読者が抱えている悩みが全て解決されるか」を最優先で考えるようにします。
ブログ記事を書く手順③:記事を書き終えた後にやること
本文を全て書き終えたら、無事に記事が完成…というわけではありません。
記事の公開ボタンをクリックする前に、最低限やるべきことが2つあります。
- 記事の装飾
- 記事の推敲
この2つは記事を書き終えたら必ず行うように習慣づけをしましょう。
記事の装飾
記事の本文を書き終えたら、読者にとって読みやすい記事を目指すために、装飾をしていきます。
- 色、太字、マーカーなど文字装飾
- 画像の使用
- グラフや表の使用
- 吹き出しの使用
などを通じて、記事のデザイン面を整えていきましょう。
ブログ読者は文章をちゃんと読んでくれることは少なく、大抵の場合は流し読みや飛ばし読みをするものです。
だからこそ、読者の視点を止めてあげて、ちゃんと本文を読んでもらえるような仕掛けを施したり、本文をちゃんと読まなくても内容が理解できる(価値を受け取ってもらえる)ための装飾が必要となります。
ブログのジャンルやターゲットにも寄りますが、スマホで見たときに一画面が全て黒文字でびっちり埋まっているという状況は避けたいですね。(ビジネス系の読み物など、読者の属性やブランディングによってはその限りではありません)

記事をちゃんと読まれる、離脱されないというのはSEO的にも大事なポイントです!
記事の推敲
記事の本文を書き終えて公開ボタンを押す前に、必ず「推敲」をするようにしましょう。
推敲と聞くと、誤字脱字や日本語表現のチェックをイメージされるかもしれませんが、それだけではありません。
- 読者の悩みは完璧に解決されているだろうか
- 他のライバル記事と比べて見劣りしていないだろうか
- 読みやすさは問題ないだろうか
- 情報量は適切だろうか
などなど、最終的に記事を読んだ読者が「このコンテンツのファンになるか」という点まで含めて、推敲をしてあげましょう。
場合によっては、最初に決めた構成が変わることになったり、新しい検索意図を見つけることで内容も変わってくるかもしれません。
もちろん、後から記事の修正をすることはできますし、実際に投稿済みの記事をリライトする機会は増えることになりますが、公開する前に「この記事で本当に読者を満足させることができるのか」という視点で推敲をするようにしましょう。

トレンドキーワードを狙うなど「公開の速さ」が鍵となる場合は、臨機応変に対応しましょう。
読まれる記事ライティングのポイント

次に、読者にちゃんと記事を読んでもらいやすくなるライティングのポイントを紹介していきます。
ブログ記事だけでなく、ビジネスライティング全般に通ずるポイントです。ぜひご参考にしてください。
結論から書き始める
まず結論から書き始めましょう。
読者は結論がわからない状態で文章を読み進めることに対し、無意識にストレスを抱えますし、求めている答えがなかなか出てこないと感じた時点で、記事から離脱される可能性があります。
まずは結論を書いて、その上で理由や具体的な説明に入るようにしましょう。
できるだけ簡潔に書く
「ちゃんとした文章を書こう」と思うと、つい無駄な言葉を使ってダラダラと読みにくい文章を書いてしまいがちです。
例えば、
- してしまいがち→しがち
- SEOを意識するということを徹底する→SEOの意識を徹底する
- 重要となります→重要です
と修正するだけでも、非常に読みやすく意味が伝わりやすい文章に変えることができますね。

推敲の時は「もっと簡潔に伝わりやすくできないか」を意識しましょう!
特に「〜するように」とか「〜ということ」といった形式語を取り除いてあげるだけで、スマートな文章になります。
ぜひ「簡潔な文章」を書くことで、意味が伝わりやすいライティングを徹底しましょう。
読者にとって適切な言葉遣いを心がける
ブログを書き始める前に、記事の目的や「誰にどんな価値を届けるのか」を先に決めるとお伝えしましたが、記事のターゲットによって、書き方も内容も、文章中で使う単語や言葉遣いも変わってきます。
例えば、初心者向けの記事では上級者向けの記事に比べても、わかりやすく平易な言葉が求められますし、女性をターゲットにした記事であれば感覚的な表現や擬音語を増やすなどの工夫があってもいいですよね。
エンタメ系のブログと、ビジネス系のブログでは、文の固さも変わってきます。

このブログは敢えて固めなライティングを心がけています。
平仮名とカタカナ、漢字のバランスを意識する
文章を読むことが好きな人はそう多くありません。
横文字に拒絶反応がある人も多いため、あまりにもカタカナが続く文章は読者から敬遠されますし、漢字ばかりの文章も同様に難解そうな印象を与えてしまいます。
逆にひらがなばかりの文章も、パッと見たときに、視覚的に意味をキャッチすることが難しく、結果として読みにくい文章に見えてしまうでしょう。
漢字やひらがなは無意識で使うことが多いので、自分の書いた文章は「読みやすさ」の観点からチェックをする習慣をつけましょう。
同じ語尾を繰り返さない
「〜ました。〜ました。〜ました。」や「〜です。〜です。〜です。」といったように同じ語尾が連続すると、文章にリズム感が欠けてしまい、読者に対し無意識にストレスを感じさせます。
推敲の際には、同じ語尾が連続している部分を見つけたら、異なる語尾に変換できないかという視点も大切にしましょう。
主語と述語を一致させる
特に長文を書いている場合は、1つの文章内で主語と述語が一致しなくなったり、あるいは複数の主語を混同して使用してしまう場合があります。
例えば、
- 電車が遅延して遅刻しました。
- 遅刻の原因は電車の遅延です。
この2つの文章のうち意味がスッと入ってくるのは後者だと思います。
前者も意味が理解できなくはないですが、「遅延して」の主語は「電車」になり「遅刻した」の主語は「私(文中では省略)」になります。
つい思いつくままに文章を書いていると、主語と述語がゴチャゴチャしかねないので、主語と述語がきちんと一致するように気をつけましょう。
指示語を使いすぎない
「これ」「それ」「この」といった指示語は便利ですが、読者にとっては「これ」が何を指しているかわからなくなるため、文章が分かりづらくなります。

現代文のテストでも「『これ』は何を指しているか述べよ」という問題は定番ですからね…!
またSEOを考慮しても、狙ったキーワードやそれに関係のある共起語が文中に多く含まれる方が、Googleからの評価も高くなる可能性があります。(もちろん、読者にとって自然な範囲で、です)
そのため、なるべく指示語を使いすぎず、具体的な言葉に置き換えることを心がけましょう。
結果が出ない人にありがちな記事の書き方

最後に、結果が出ない人にありがちな記事の書き方をまとめて終わりとします。
もし当てはまっているものがあれば、今この瞬間から改善していきましょう。
いきなり本文から書き始める
記事を書く時、タイトルや構成を決めることなく、いきなり本文を上から書き始めると、記事の構成がぐちゃぐちゃになって、検索者にとって価値のあるコンテンツから遠ざかってしまいます。
まずは、当記事でもお伝えしたように、キーワード選定と検索意図と狙いを洗い出した上で、タイトルと見出しを先に作ってから記事本文を書き始めるようにしましょう。
書き終えた記事を自分でチェックしない
意外とあるあるなのが、記事を書き終えたら推敲を全くしないで、すぐに公開をして後は放置というパターン。
記事を最後まで書き終えるとヘトヘトになってしまって、チェックするのも面倒だし、できればすぐに公開しちゃいたいという気持ちはわからなくもないですが、ビジネスとしてブログをやるのであれば、最低限のプロ意識は持ちたいものです。
自分が書いた記事に誤字脱字がないか、本当に検索者のニーズを満たせているのか、もっと良い記事にできる方法はないかどうかをぜひ最終チェックする習慣をつけましょう。
文章に個性を出そうとしすぎる
検索エンジンで評価されるためには、他のサイトにはない独自性が必要だという意見もあります。
確かに他のサイトにはない着眼点や情報は大事ですし、他サイトのコピーのような記事を生み出すのはNGですが、個性を出そうとするあまり、読み手を置き去りにした無価値なブログ記事になってしまうリスクもあります。
大事なのは、読者ファーストの姿勢です。
この記事の読者はどんな情報を求めていて、何を解決したいと思っているのか。そこと真摯に向き合っていくことで、自ずと記事ならではの個性は出てくるものです。
日本語として文法がおかしいところが多々ある
多少の文法ミス程度は許容されるかもしれませんが、そもそも読むに耐えないレベルの日本語しか書けないと、そもそもブログで結果を出すことは難しいです。
ブログで結果を出す上では、際立った文才は特に必要ありませんが、読者にとって読みやすい日本語を書く最低限の能力は必要となります。
とはいえ「正しい文章が書けない」のは、注意力が不足しているのと、文章を書いたり読んだりする経験が不足していることに起因するものです。
- 記事を書きながら慣れていくこと
- どんどん良い文章に触れること
この辺りを習慣化しつつ、読者視点でのライティングを徹底していきましょう。
まとめ
読まれるブログ記事を書く際には、自分目線ではなく「どうしたら読者に価値を届けられるか」という視点で考える癖をつけましょう。
そのためには、まずはしっかりと手順に沿って、検索者に価値を届けられるコンテンツの構成を練ることが重要です。
どうやって記事を書いていいかわからない場合は、ぜひこの記事の内容を参考にしてくださいね!